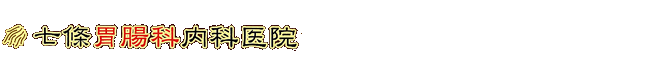

 |
|
| A.
�͂��A���v�ł��B ���@�ł͗��@����Ă���f�@�܂ł� �@�@ �@�@�҂����Ԃ��ł��邾���Z������H�v�̈�Ƃ��� �@�@ �@�@�\��f�@����{�ɐf�Â������Ă���܂����A���߂Ă̕��� �@�@ �@�@�}�Ȕ��a�Ŏ�f�����F�l�̗��@�ɔ��������Ԙg�� �@�@ �@�@�\�ߌ�p�ӂ������Ă���܂��̂ŁA��t���ԓ��ł���� �@�@ �@�@�������łɂȂ��Ă����܂��܂���B�������߂Ă̕��� �@�@ �@�@�����������f�����鎞�Ԃ��K�v�ƂȂ�A�f�@�܂łɑ��� �@�@ �@�@�����Ԃ����������܂��̂ŁA��Ƃ�������Ă����@���������B |
|
| A.
�������\�ł��B���@�̃X�^�b�t���Ή��������܂��̂� �@�@ �@�@�d�b�ł��s���̗ǂ������� ���\���t�����������B �@�@ �@�@�����}�Ȃ��p���Ăł��ƁA�A���\���č���ł���܂��̂� �@�@ �@�@�����߂��̎��ԑтɂȂ��Ă��܂����Ƃ��������� �@�@ �@�@�����ɗ]�T�������Ă��\���������Ƃ������߂������܂��B �@�@ �@�@�܂����f�����Ɍ��炸�A����I�ȓ���������������]�̕��� �@�@ �@�@�}�ȏǏ�ň݃J��������]�����ꍇ�i���f�̕��ł��j�ł� �@�@ �@�@�܂��͂P�{���d�b������������Α��₩�ɑΉ��������܂��B |
|
| A.
�\�������܂���B�������̂Ƃ���A���x�����͌����݂̂� �@�@ �@�@�����Ă��������Ă���܂��B�����߂������ɃJ�[�h�ł����Z �@�@ �@�@�ł���悤�ɏ�����i�߂Ă���܂��B |
|
| A.
�͂��B���@�ɗאڂ��ĉE�ׂɑ���ǐV�ۓX���������܂��B �@�@ �@�@�����Ȃ瓖�@�ŏ������ꂽ�����ׂĎ�葵�����Ă���A �@�@ �@�@����ɂ��ĂƂĂ��D�������J�ɐ������Ă���܂���B |
 |
|
| A.
���{�l�̃s�����ۊ����҂͖�6000���l�ƌ����Ă��� �@�@2�l�ɂP�l���z���Ɛ��v����Ă��܂��i����҂ł�8�����z���j�B �@�@�z���҂̊���������1�O�Έȉ��̗c�����ƕ��͂���Ă���A �@�@���l�ł͖Ɖu�͂��������߂ɁA�ݓ��Ƀs�����ۂ������Ă��Ă� �@�@�蒅���邱�Ƃ��ł��������������Ȃ����Ƃ��킩���Ă��܂����B �@�@�܂�s�����ۊ����҂͊F�A�c��������̎��������ł���A �@�@��x���ۂɐ�������ƍĊ����͋N����Ȃ��ƍl���Ă��������B �@�@���ۗÖ@�̓K����������ł���A�݊��Ƃ̊ւ�������A �@�@���Ў��Â����邱�Ƃ������߂������܂��B �@�@��������A���܂�݂̈̒��q�ǂ��ɐl�����ς��܂���B |
|
| A.
���ۗÖ@�͂R��ނ̖���P��2��A�P�T�ԑ����ĕ��p���܂��B �@�@���̂�����2��ނ��s�����ۂɌ��͂̍����R�ۍ܂ł��̂ŁA �@�@�W���I�ɕ��邱�ƂŁA 10�`20���̕��ɉ������ւ��A �@�@5���̕��Ɍ��̒��̋ꖡ�� ����邱�Ƃ�����܂��B������ �@�@����������x�͌y���A���Â𒆎~����悤�Ȃ��Ƃ͂���܂���B �@�@����p�͉����N���Ȃ������Ƃ��������命���ł��̂ł����S�������B �@�@�A���A���i���牺���̎��̕���y�j�V�����A�����M�[�̊����� �@�@������͐T�d���^�ƂȂ�܂��̂Ŏ��O�ɂ����k���������B |
|
| A.
�ˑR�A���ǂ���q�f�Ɖ����̏ꍇ�͊������ݒ������^���܂��B �@�@�������ݒ����ɂ͉ď�ɑ����ې��i�T�����l���ہA�����r�u���I�A �@�@�L�����s���o�N�^�[�A�a�����咰�ۂȂǁj�̂��̂ƁA �~��ɑ��� �@�@ �@�@�E�C���X���̂��̂�����܂��B �E�C���X�̒��ł������͂����ɋ����� �@�@ �@�@���ʂŏW�c�������邱�Ƃ��� �u�m���E�C���X�v���ƂĂ��L���ł����A �@�@���ɂ��A�f�m�E�C���X�A �T�|�E�C���X�A���^�E�C���X�A�A�X�g���E�C���X �@�@�Ȃǂ������̏ꍇ������A�m���E�C���X�Ɨގ��̏Ǐ��悵�܂��B �@�@�m���E�C���X�͈ȑO�͏��^���`�E�C���X�iSRSV)�Ƃ������O�ł������A �@�@2003�N�ɖ��O�����肳��Ă���͋}�ɗL���l�ɂȂ��Ă��܂��A �@�@�u�m�����������ǂ����ׂė~�����v�Ƃ����v�]�������Ȃ�܂����B �@�@�m���E�C���X�͊������甭�ǂ܂�1�`2��������܂����A�������Ă� �@�@���ǂ��Ȃ����Ɓi�s���������j�����\���邱�Ƃ��m���Ă��܂��B �@�@�u�q�����m���ɜ�����̂Ŏ����������ł́H�v�Ǝ�f�������� �@�@�悭�������܂����A���͎�f�������̏�Ńm�����������Ɛf�f�ł��� �@�@���@�͍��̂Ƃ���܂�����܂���B�u�m����������Ȃ��v�Ƃ��������� �@�@���̊Ԃɂ��u�m���������v�Ǝv�����ރP�[�X���������Ă��܂��B �@�@�m���̓���͂����ԂƔ�p��ɂ��܂Ȃ���ΐf�f�͉\�ł����A �@�@��������킯�ł��Ȃ��A���ʂ��o�鍠�ɂ͊������Ă��܂��̂ŁA �@�@���ÂɊւ��Ă̐f�f�I�Ӌ`�͒Ⴂ�ƍl���Ă��������B�厖�Ȃ��Ƃ� �@�@�����̓���ł͂Ȃ��A���₩�ȑΏǗÖ@�ŏ��ɏ��邱�ƂƁA �@�@���͂ւ̍L������ŏ����ɗ��߂�z����H�v�ɓw�߂邱�Ƃł��B |
|
| A. �����ɂ́A�r�t�B�Y�X�ۂɑ�\�����P�ʋہA�E�G���V���ۂɑ�\����� �@�@���ʋہA�̒��ɂ���Ăǂ���ɂ��ω�����یQ��3�Q�ɑ�ʂ���A �@�@��l�������9000������Ƃ�������ۂ������Ő��͑��������Ă��܂��B �@�@���N�Ȓ��͑P�ʋۗD���Ŏ_���ł����A�H�����̗����^���s���A �@�@�X�g���X�����܂�ƈ��ʋۗD�ʂƂȂ�A���J�����ɌX���܂��B �@�@���̌��ʁA�������s���i�݁A�֔�≺���݂̂Ȃ炸�A���r��� �@�@�Ɖu�͂̒ቺ�������N�����܂��B���ł������֔�͈��ʋۂ̉����ƂȂ� �@�@�Ȓ������������܂��B�܂��ӊO�ƒm���Ă��܂��A �@�@�ԕ��ǂȂǂ̃A�����M�[�����̔��a�ɂ��[���W������܂��B �@�@�}�ɉԕ��ǂɂȂ����ꍇ�͒����̈��������������m��Ȃ��̂ł��B �@�@���ʋۑ����̃T�C���Ƃ��ẮA�L�Q�����̔����ɂ�蕠�ɁA���ɁA�߂܂��A �@�@�ւ�I�i���̓����������A����������A������A���L�A���r��A������ �A �@�@���ׂ��J��Ԃ��Ȃǂł����A�������ōł������̂͑咰���̔����ł��B |
|
| A. �ŋ߁u�v���o�C�I�e�B�N�X�v�ƌ������t���悭���ɂ���Ǝv���܂��B �@�@����͗L�Q�Ȕ������̔r����ړI�Ƃ����R�������Ƃ͑S���t�̊T�O�ŁA �@�@�����̑P�ʋۂȂǁA�̂ɗL�v�Ȕ������̑��B�𐄐i���邱�Ƃł��B �@�@�P�ʋۂ𑝂₷�̂ɂ����Ă����̐H�i�̓��[�O���g�ł����A �@�@�r�t�B�Y�X�ۂ��͂��߂Ƃ��鑽���̓��_�ۂ͈ݎ_��_�`�_�Ɏキ�A �@�@���ɓ��B����O�ɑ啔�����E�ۂ���Ă��܂��܂��B �����ŏo���邾�� �@�@�����悭�������܂ܒ��ɓ͂���|�C���g�͋ł͂Ȃ��H��ɐH�ׂ鎖�ł��B �@�@���̂Ȃ�H����͑��̐H�ו��������Ĉݎ_�����܂��Ă��邩��ł��B �@�@���[�O���g��200g2�T�ԘA���ŐH�ב�����Ɩ�10���P�ʋۂ� �@�@�����܂������z�I�Ȓ��������ێ�����ɂ͖����⋋���邱�Ƃ���ł��B �@�@����Ƃ�����厖�Ȃ��Ƃ̓��[�O���g�P�Ƃł͂Ȃ��I���S���ƈꏏ�� �@�@�ێ悷�邱�Ƃł��B���ʋۂ͓��ނ⎉�b���D���ł����A �@�@�P�ʋۂ̓I���S����H���@�ۂ���D���ł��B�I���S���ܗL�H�i�� �@�@���[�O���g�Ƃ̑������猾���A�����S�A�o�i�i�A�I�����悭�A���ɂ� �@�@�哤�H�i�A���ڂ��A���܂˂��A�ɂ�ɂ��A���ȕ��Ȃǂɑ����܂܂�Ă��܂��B �@�@�܂��A���X��ݖ��A���̂Ȃǂ̔��y��������`�[�Y��Ђ����Ȃǂ� �@�@���y�H�i���P�ʋۂ̖����ł��B���ł��ŋ��͉��Ƃ����Ă��u�[���v�ł��B �@�@�[���ۂ͓��_�ۂ̒��Ԃʼn�E�ƌĂ��k��L���Ă��邽�߈ݎ_�ɂ����� �@�@�������܂ܑ咰�ɓ��B���܂��B�[���ۂɊ܂܂��i�b�g�E�L�i�[�[�ɂ� �@�@���ɑ����̌��N���ʂ�����ł������߂̐H�i�ł��B�����[���ۂ� �@�@���̏�ۂɂ͂Ȃ�Ȃ��̂Ŗ����P�p�b�N�H�ב�����悤�ɂ��܂��傤�B |
|
| A. �r�ւ̊Ԋu�͂ЂƂ�ЂƂ�̑̎��A�H�����A���Ȃǂɂ���Đl ���ꂼ�� �@�@�ł����� ��T�ɂ͌��߂��Ȃ��̂ł����A���{���Ȋw��̒�`�ł� �@�@�u3���ȏ�r�ւ��Ȃ��ꍇ�A�܂��͖����r�ւ������Ă��c�֊��������ԁv �@�@�Ƃ���Ă��܂��B�֔�ɂ͎�ᇂȂǂŒ��̒ʉߏ�Q�ɂ���Ă����� �@�@�w�펿���֔�x�ƁA ���炩�̗��R�Œ��̉^���@�\���ቺ���Ă����� �@�@�w�@�\���֔�x�Ƃ�����A ��ʓI�ɕ֔�̌����Ƒ�ŔY�܂���Ă���̂� �@�@��҂̕��ł��B �X�ɋ@�\���֔�ɂ́w��ߐ��x�Ɓw�K�����x������A �@�@�K�����֔�� �����̗͒ቺ�Ȃǂɂ���Ă�����u�o�ɐ��֔�v�ƁA �@�@�X�g���X�Ȃǂ������ƂȂ� �u�z�����֔�v�A�ֈӂ��䖝����l�ɋN����₷�� �@�@�u�������֔�v�Ȃǂɕ������܂��B �@�@���Ɂu�h�ցv�ɂ��Ăł����A����͈ݒ��a�̐��p��ł͂���܂���B �@�@��ʂɂ́u���ǂ̓����ɂ��т�����w�h���̗l�ȌÂ��ցv�Ƃ��� �@�@�������Ă���悤�ł����A����͌��ł��B����従��^�����ቺ����� �@�@�ʉ߂Ɏ��Ԃ������邽�ߒ����̑ؗ����Ԃ������Ȃ�A�F�X�Ȍ��N��Q �@�@�i�����K���a�A�Ɖu�͒ቺ�A�咰�������Ȃǁj�̗v���ɂȂ�܂����A �@�@���ǂɓ\��t�����艻�̂悤�ɑ͐ς��邱�Ƃ͂���܂���B�����ł��� �@�@�u�h�ցv�͒��x�̂Ђǂ��֔���w������p��ƍl���Ă��܂��B |
|
| A. �s�̂̉��܂ɂ͖w�ǂ̏��i�Ɂu�r�T�R�W���v�u�Z���m�T�C�h�v �@�@�Ƃ����������܂܂�Ă��܂��B�����͒��ړI�Ȓ��h���� �@�@�r�ւ𑣂����߂ɕ��ɂ��₷���A�܂��x�d�Ȃ�g�p�ɂ�� �@�@�K�����i��Ȃ��ł͔r�ւł��Ȃ��j�ƂȂ鋰�ꂪ����܂��B �@�@�X�Ɏg��������ƌ����������Ȃ�n�߁A���ʂ����߂邠�܂�� �@�@����ʂ������A���̌��ʕ���p�̊댯�ɂ��炳��Ă��܂��܂��B �@�@���ɔD�P���͗��Y��U�����鋰�ꂪ����g�p�͌��ւł��B �@�@�܂肱���͋ꂵ���Ƃ��̂��̏ꂵ�̂��I�ȉ��}���u��ł���A �@�@�g�������Ă����{�I�ȕ֔�̎��̉��P�ɂ͂Ȃ�Ȃ��̂ł��B �@�@�����Ԃɑ̂ɐ��ݕt�����֔�Ȃɂ��ẮA����Ë@�ւ� �@�@�Z���I���ƒ����I�ȑ̎����P�s���Đi�߂Ă����Ȃ���� �@�@���{�I�ȕ֔邩��̒E�p�͓�����̂Ȃ̂ł��B |
 |
|
| A. ���@�ł͓���������������S���ɗ\�߁A�~�ł�̉��Ȃǂ� �@�@�@ �@�@�����ǂ��F�b�N�����Ă���܂����A�ŐV�̏��Ő������ �@�@���S�������Ă���܂��̂ŁA�ǂ��������S���������B �@�@�������{�̂̏��ł͂P��I�����Ƃɉߐ|�_�ɂĎ��{���Ă���A �@�@�����Ȃǂ̏��u��͈ꕔ�������f�B�X�|�i�g���̂āj�ł��B �@�@�i����Ȃ��̂̓I�[�g�N���C�u�ŏ��ł��܂��j |
|
| A. �ߔN�ɊJ�����ꂽ�o�@�������́A�Q�[���ƂȂ�������˂���r�I �@�@ �@�@�������ɂƂ��Ă͏]���@��� �y�� �����@�Ƃ��ċr���𗁂тĂ܂��B �@�@ �@�@���@�ł��������瓱�����āA�I�����Ă���������悤�ɂ��Ă܂����A �@�@ �@�@�A�����M�[���@���▝���@���Ȃǂ� �@�o���������ɂ� �s�����ŁA �@�@ �@�@�}���ɂ��₷���A�������Đh�������ɂȂ��Ă��܂��܂��B �@�@ �@�@�@���u�ɕό`����������A�@�̎�p�̊�����������ł� �@�@ �@�@�}������o���Ȃ��ꍇ������܂��B�܂��A�����͏o���Ă� �@�@ �@�@�~���Ȃǂ̎��Â��ł��Ȃ����Ƃ����_�ƌ�����ł��傤�B �@�@ �@�@�����ő�̎�_�́A�]���̌o���������ɔ�ׁA�a�䂦�� �@�@ �@�@�掿���啝�ɗ�邱�Ƃł��B���ǂ���Ă����Ƃ͂������s�� �@�@ �@�@�n�C�r�W�����摜�Ɣ�r����Ɖ_�D�̍�������܂��B �@�@ �@�@�܂�o�@�������ł͐��I����Ŋώ@���Ă��A���������̊��� �@�@ �@�@�����Ƃ���Ă��܂��S�z�������ƌ����܂��B �@�@ �@�@����ȊO�ł��̕��@�Ō��������ꍇ�A �@�@ �@�@���̊댯�x�������Ȃ邱�Ƃ͌����܂ł�����܂���B �@�@ �@�@�]���Ċ���S�z���Č�����������A�N��Ō����� �@�@ �@�@40�Έȏ�ŏ���̏ꍇ�͏]���̌o���������������߂������܂��B |
|
| A. �����͖��Ȃ��s���܂����A�S���I�Ȗʂ��l�����܂��ƌ������R�� �@�@ �@�@�}���K�v�����Ȃ���A�Ȃ�ׂ��������Ԓ��͔����Ă��������� �@�@ �@�@������낵�����Ǝv���܂��B���ɏo���ʂ̑������o������ �@�@ �@�@�����ɂ��������ł͌����ɂ���ĕs���x���������Ƃ�����܂��B |
 |
|
| A. �ȑO�́u���Ă��v���u�t�����H�����v�ƍl�����Ă��܂������A �@�@�ŋ߂ɂȂ�A�t�����H�����������Ă��ǏȂ��l������A �@�@�t�ɋ��Ă����Ђǂ��Ă��������I�ȐH�������Ȃ��l���ӊO�� �@�@�������邱�Ƃ��킩���Ă��܂����B��҂��uNERD�v�ƌ����܂��B �@�@�X�ɂ��������āu�ݐH���t���ǁiGERD)�v�ƌĂ�ł��܂��B �@�@NERD��50�Έȉ��̏����ɑ����X��������A�t�����H������ �@�@���ɂ悭�݂���悤�ȐH���ƈ݂̐ڍ����̊ɂ݂����Ȃ��A �@�@���̎��Ԃ͐H���m�o�ߕq�ɂ����̂ƍl�����Ă��܂��B |
|
| A. �ݐH���t���ǁiGERD)�͈ݎ_�̐H�����t���ɔ����Ǐ�Q�̑��̂ŁA �@�@�T�^�I�Ǐ�Ƃ��ẮA���Ă��A�ێ_�i�����ς������������Ă���j�ł����A �@�@���̑��ɂ��A���Ɂi���S�Ǘގ��j�A�����̊P�A�A�̈�a���A�����ꐺ�A �@�@���ɁA���ɂȂǑ��ʂȏǏm���Ă��܂��B���̂��߂ɍŏ��� �@�@�ʂ̕a�C���^���鎖�������A�ŏI�I�ɐf�f���t���܂łɎ��Ԃ� �@�@�v���邱�Ƃ�����������܂���B�A���H������݊��̈ꕔ�ł� �@�@GERD�Ǐo�����邱�Ƃ�����A�f�f�̂��߂Ɉ݃J�����͕K�{�ł��B |
 |
|
| A. �_�X�|���[�v��40�`50�Α�𒆐S�ɍŋߑ����X�����݂��܂��B �@�@�_�͏����ɑ����݂��܂����|���[�v�͒j����������܂���B �@�@�_�X�|���[�v�́A���̔����ȏオ�R���X�e���[���n�ł���A �@�@�傫����5mm�ȉ��ŕ�������ꍇ�̓R���X�e���[���|���[�v�� �@�@���邱�Ƃ��w�ǂł��̂ŏ�����������S�z�͂���܂���B �@�@�P����6�`10mm�̂��̂� �T�d�ɒǐՂ��Ă����K�v������A �@�@�P����10mm�������̂́A CT,ERCP�AMRCP,EUS�Ȃǂ� �@�@�����������ĕ��j�����肵�� �����悢�ł��傤�B �@�@���v��20mm�ȏ�̂��̂ł͖�80�������ł��B �@�@���̂悤�Ɍ������Ȃ��قǁA�܂��傫�����傫���ق� �@�@�����̉\���������Ȃ�܂��̂ŁA�Ǐ�̗L���ɊW�Ȃ� �@�@����I�ȕ����G�R�[�����ł̒ǐՂ� �ƂĂ��d�v�ɂȂ�܂��B |
|
| A. �Ⴂ�܂��BHCV�R�̂��z���̈Ӗ��́A�m���ɉߋ��Ɋ��������ł����A �@�@���̑����̕������݂������������Ă���A�E�C���X�ʂ�^�C�v�A�����x�� �@�@�ڂ������ׁA�o�ߊώ@�ł����̂��A���邢�͒����Ɏ��Â��ׂ��Ȃ̂����A �@�@HCV�R�A�R������ ��j�_���������iNAT�j �A�����G�R�[�����Ȃǂ� �@�@���肵�܂��B |
 |
|||||||||||||||||||||||||
| A. �w�l�Ȃł͗�����q�{�Ȃǂɒ��ڊ֘A����a�C�i������ᇁA �@�@�q�{���A�q�{�؎�A�q�{�����ǂȂǁj�𒆐S�ɐf�Â���̂ɑ��A �@�@�@ �@�@�������Ȃł͏������L�̋@�\�s����̑S�̂̕ω��Ƃ��đ����A �@�@�@ �@�@���Ȉ�̗���Őf�@����ƍl���Ă��������B |
|||||||||||||||||||||||||
| A. ����̈�ẤA�j����Ώۂ̒��S�Ƃ�����w�����̒m���� �@�@���̂܂����ɂ��K�p���Ă���A�������A�f�f�⎡�Âɂ����� �@�@�����̎��_����������邱�ƂȂ��s���Ă���̂�����ł��B �@�@�ŋ߂ɂȂ�A�j�����ʂ̑���̋@�\�ɂ����͐����������āA �@�@���̂��ߌ����⎡�Â̔����ɂ��j����������Ƃ����l������ �@�@�悤�₭�F������n�߂܂����B �@�@�j���͐����w�I�Ɍ����Ɛ����F�̂̈Ⴂ�ŋ�ʂ���܂����A �@�@���U�̉c�݂ɂ����Ă͏����z�������ɑ傫�ȍ�������܂��B �@�@�����͂��̐��z�������̕ϓ��������A���B��݂̂Ȃ炸 �@�@�S�g�̑���ɗl�X�ȉe�����y�ڂ����߁A�a�C�̐f�f�⎡�ÁA �@�@�\�h�̏�Ő藣�����Ƃ��o���Ȃ��̂ł��B �@�@�Ƃ��낪���ۂ̈�Ì���ł́A���̂悤�Ȑ�����Â̎��_�� �@�@�f�Â��Ă�����Ȉ�͋ɁX�����ł���A�܂����Ȃ̐��m���� �@�@�L�����Y�w�l�Ȉ���H�L�ł��B�����Ƃ����݁A�S���ł��� �@�@�K�v���������邻�̑����͎Y�w�l�Ȃ̐搶���ł����A �@�@���ꂩ��^�̐�����ÂW�����邽�߂ɂ́A�j���o���� �@�@�f�ÂɌg��钆���珗����Â̂������Nj����ׂ��ł���A �@�@�������d���������Ȉオ���S�ƂȂ��Đ��i���Ă������Ƃ� �@�@���n����ƍl���Ă��܂��B �@�@���@�ł͊J�@������A���́u������Áv���d�������H���Ă��܂��B |
|||||||||||||||||||||||||
| A. �����z�������̑�\�ł���G�X�g���Q���̎�Ȑ�����p�� �@�@�������B��̔����@�\�ێ������S�ł����A���̑��ɂ� �@�@���̕\�ɂ��������܂����l�ɁA���X�̐��̂̉c�݂̒��� �@�@�ی�I�ȍ�p�𑽂��L���Ă��܂��B���̂��ߒ����I�Ɍ���� �@�@�o�܂ł̏����͒j�����������̕a�C�������Ă���� �@�@�����܂����A�o���ɗ����@�\���}���ɒቺ���n�߁A�₪�� �@�@�����̃G�X�g���Q���ʂ͒j���ȉ��ɂ܂Ō������Ă��܂��܂��B �@�@���̌��ʁA�����ł͕o�����ɂ���܂ŕی삳��Ă������ǂ� �@�@���A�_�o�Ȃǂ����X�ɐ����n�߁A��X�̕ω�������܂��B �@�@�܂��Z���I�Ɍ���ƁA�G�X�g���Q���͐��������̒��� �@�@���o��ɏ㏸���r����Ɍ�������A�b�v�_�E�����J��Ԃ��Ă���A �@�@���̕ϓ������X�̑̒��ɑ傫���֗^���Ă��܂��B �@�@�����O�̃C���C���A��s����Ȃǂ͂��̓T�^��ƌ����܂��B |
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| A. ���������͒������b�ƃR���X�e���[���ɑ�ʂ���A�O�҂� �@�@��ɃG�l���M�[�Ɏg����̂ɑ��A��҂́A�זE���� �@�@�z�������̍ޗ��ɂȂ�ȂǁA���ɑ�Ȗ������ʂ����Ă��܂��B �@�@�R���X�e���[���ɂ͈��ʂ̂k�c�k�ƑP�ʂ̂g�c�k������܂��B �@�@�k�c�k�͌��ǂɕt�����ē����d���Ȃǂ̌����ƂȂ�A�t�� �@�@�g�c�k�͌��Ǖǂɗ��܂����R���X�e���[����|�����܂��B �@�@���͂k�c�k���̂����ʂȂ̂ł͂Ȃ��u�_���k�c�k�v�ɂȂ������ɁA �@�@�{���̊댯���q�ƂȂ�̂ł����A���݂̐f�f��͂k�c�k�l�� �@�@140mg�ȏ�̏ꍇ���������ǂƂ��A�H���w�����Ȃǂɂ�� �@�@���ÑΏۂɂȂ��Ă��܂��B�ُ퍂�l���p������Ɠ����d�����i�s�� �@�@�S�؍[�ǂ�]�[�ǂǂ���댯�x�����܂邱�Ƃ͎����ł����A �@�@�t�ɒႷ���Ă��]�o���̊댯�����܂邱�Ƃ��m���Ă��܂��B �@�@�����͕o����萫�z�������ł���G�X�g���Q�����������n�߂܂��B �@�@����Ƃ��̍�p�̈�ł���LDL�̗}�����ʂ��Ȃ��Ȃ� �@�@���̎��������ɃR���X�e���[�����}���ɏ㏸���Ă��܂��B �@�@50�ΑO��̏��������N�f�f�Ȃǂŋ}�ɍ������ǂƌ����n�߂邱�Ƃ� �@�@�����̂͂��̂��߂ł��B���ꂪ�����Ɉ��|�I�ɑ����݂��闝�R�ł��B �@�@�ŋ߂̌����ł́A�R���X�e���[���l�ƐS�؍[�ǂ̔��a���ɂ͐���������A �@�@�j���͒�l�قǔ��a���ɂ����̂ɑ��A�����ł͒Ⴗ���Ă����a���₷���A �@�@���R���X�e���[���l��200�`220mg�̎��ɍł��S�؍[�ǂ̔��a�����Ⴂ �@�@���Ƃ��킩���Ă��܂����B�܂菗���ł͓K�x�ɂ������ق������S�Ȃ̂ł��B �@�@�Ƃ͌����Ă���������̂͋֕��ł���A�����d���\�h�̂��߂ɂ� �@�@�����܂ł��H���Ɖ^������{�ł��B �@�@�@�@�H���@�ۂ𑽂��܂ސH�i��ێ悷�� �@�@�@�E�E�E�H���@�ۂ͏����ŃR���X�e���[���̋z����}���铭��������B �@�@�@�A�L�_�f�^�����p������ �@�@�@�E�E�E���މ^���R�O��/�T�R��̌p����HDL��������B �@�@�@�B�a�H���S�i����DHA�̑��������j�̐H�����ɂ��� |
|||||||||||||||||||||||||
| A. ���������u�X�N���v�Ƃ͕o�O��̂P�O�N�Ԃ��w�����Ƃ������A �@�@��ʓI�ɂ�45�`55���ɑ������܂��B�����̏ꍇ�͂��̎����� �@�@�����z�������ʂ��ቺ���Ă��邽�߁A�l�X�ȕs�����N����₷���Ȃ�܂��B �@�@�Ƃ��낪�ߔN�ł�20�Α�㔼����40�Α�O���̎�N�w�ɂ� �@�@�X�N���Ǐ�Ƃ悭�����Ǐ�ŔY�ޕ��������n�߂Ă��Ă��܂��B �@�@������u�v���X�N����Q�v�i��N���X�N����Q�j�ƌ����܂��B �@�@���̌����Ƃ��Ă͉ߓx�̃X�g���X����ȗU���ƍl�����Ă���A �@�@�A�E��ސE�A�����◣���A�o�Y��玙�A�v�̗��e�Ƃ̓����� �@�@�s����ȓy�n�ł̐����ȂǁA�ߏ�ȃX�g���X���~�ς���� �@�@�z�������̃o�����X�V�[�g������Ă��܂��B�z�������ʂ͑���ĂĂ� �@�@����ȃ��Y�����������ƂŁA�X�N���Ɠ����悤�ȏ�ԂɊׂ邱�Ƃ�����܂��B �@�@���ۂ̍X�N���ł͏����z�������ʎ��̂̌����Ŕ��ǂ��Ղ��Ȃ��Ă܂����A �@�@����ł��U���͂�͂�A�ƒ�̃g���u���◼�e�̉��A�v�̑ސE�A �@�@�q���̐i�w��A�E�Ȃǂ̃X�g���X���g���K�[�ɂȂ�܂��B �@�@�����u���邢�v�ƌ����Ǐ�͗l�X�ȕa�Ԃŏo�����Ă��܂��̂ŁA �@�@�����ꍇ�͎��Ȕ��f���Ȃ��ő��߂Ɉ�Ë@�ւ���f���Ă��������B |
|||||||||||||||||||||||||
| A. �s����ɌJ��Ԃ���閝�����ɂɂ́A�ʏ�悭������ْ��^���ɁA �@�@�����Ɉ��|�I�ɑ����Г��ɁA�j���ɑ����Q�����ɂɑ�ʂ���܂��B �@�@�ْ��^���ɂ͓����p���ł̒����ԍ�Ƃ��J�ɔ�����̒���A �@�@�����肪�����œ��W�����͂̋ؓ������k���Ĕ������A�㓪���𒆐S�� �@�@�M���[�b�ƒ��ߕt������悤�Ȓɂ݂������I�ŁA�[���ɑ����݂��܂��B �@�@����ɑ��ĕГ��ɂ͌��ǐ��̒ɂ݂ł��B�X�g���X���U���� �@�@�]�̌��ǂ��g�����A�X�Ɍ��Ǖǂɉ��ǂ��N�����Ď��͂̐_�o�� �@�@�h�����邱�Ƃŋ����ɂ݂̔��삪�������܂��B�h�b�N���h�b�N���Ɩ���ł� �@�@���������������ɂ������ŁA�Q����ł��܂����Ƃ���������܂��B �@�@�Г��ɂ�20�`40��̏����̊F�l���啔���ŁA���̌����Ƃ��Ă� �@�@�����z�������ł���G�X�g���Q���̑����̉e�����l�����Ă��܂��B �@�@�Г��ɂ������肩��n�܂邱�Ƃ�����A�ْ��^�Ƃ̍����^�����݂���̂ŁA �@�@���̂Q�̋�ʂ͕K�������ȒP�ł͂���܂��A���҂̌���I�ȍ��� �@�@�Г��ɂ��̂����ƒɂ݂���������̂ɑ��āA�ْ��^���ɂł� �@�@���܂�ω����Ȃ��_�ł��邱�Ƃ��o���Ă����Ǝ��Ȑf�f�̖ڈ��ɂȂ�܂��B |
|||||||||||||||||||||||||
| A. �����Ƃ��Ă���Ə����͊y�Ɋ����A�����ƈ������铪�ɂ͕Г��ɂł��B �@�@�����̕Г��ɂɂ͂��̔���̑O�G��Ƃ������ׂ��\���A�O��������܂��B �@�@�悭����\���Ƃ��ẮA�������сA�ߐH�A������A����ԁA�S�g���ӊ��ȂǂŁA �@�@�悭����O���Ƃ��ẮA�f���C�A���ߕq�iῂ����B�Ⴊ�`�J�`�J����j�A �@�@���ߕq�i���邳��������j�Ȃǂł��B���ɔ��삪�n�܂�ƁA�����V�Œɂ݂������A �@�@�ɂ݂Ō���U��������Ƃ��h���Ȃ�A���ɊK�i���~�ł͌��ɂ�����܂��B �@�@�Г��ɂɑ��Ă͎s�̂���Ă��铪�ɖ�͖����Ȃ̂ŁA������^�����ꍇ�� �@�@���ɂɏڂ�����Ë@�ւŐ������f�f���A�������Ă��炤�K�v������܂��B �@�@�Г��ɂ̓�����ł���g���v�^�����܂͐���ނ���A���̌��ʂ͔��Q�ł����A �@�@�ő���̌��ʂ�ɂ͕���̃^�C�~���O���ƂĂ��d�v�ŁA�O������������ �@�@���킸�o���邾�����߂ɓ������邱�Ƃł��B�O�����Ȃ��^�C�v�̕��ł� �@�@���ɂ��n�܂������������̓����Œɂ݂͌y���Ă��݂܂��B�t�ɉ䖝�������� �@�@�Ђǂ��Ȃ��Ă��畞���ꍇ�͌��ʂ͔����Ȃ�A�����Ȃ��Ƃ�������܂��B �@�@�Ƃɂ�������U���ċ����悤�Ȓɂ݂����ꂽ�炷�������������ꂽ����� �@�@���p���Ă݂Ă��������B�Г��ɂł���P�`�Q���Ԃœ��ɂ��������锤�ł��B |
|||||||||||||||||||||||||
| A. ���q�˂̓��ɂ͕Г��ɂł���\�������ɍ����Ǝv���܂��B �@�@�u�����͓��Ɏ����v�Ǝ��o�����鏗���̊F�l�̖��͓��ɔ��삪 �@�@���o�Ɋ֘A���ċN���鎖�������Ɖ��Ă��铝�v���ʂ�����܂��B �@�@���̓��ɂ��ɂ̈�A�܂��͌��o�O�nj�Q�̈ꕔ�Ǝv�����݁A �@�@�䖝���邵���Ȃ��ƍl���Ă�����������悤�ł����A���͂��̓��ɂ� �@�@�Г��ɂł��邱�Ƃ������̂ł��B������u���o�֘A�Г��Ɂv�ƌ����܂��B �@�@�����̎��ɋN����Г��ɂ́A����ȊO�̎��Ɣ�ׂ�ƒɂ݂������� �@�@�������Ԃ��������Ƃ������A��̌��ʂ���∫���X��������܂��B �@�@���̂��ߐ����̎��́A�O�����������炢���ȏ�ɑ��߂ɓ���������A �@�@�����Ȃ��Ƃ������d����Ǝ��͑�����グ���肷��H�v���K�v�ł��B �@�@�܂��D�P���ł͏����̂��̎����Ɉꎞ�I�ɑ����邱�Ƃ�����܂����A �@�@�D�P�U�����ȍ~�ł͑啔���̕��ŕГ��ɔ��삪�y���A�������܂��B �@�@���̗��R�Ƃ��Ă͔D�P���ł̓G�X�g���Q���i�����z�������j�ʂ������܂� �@�@�������邽�߂ƍl�����Ă��܂��B�����ďo�Y�ɂ��G�X�g���Q���ʂ� �@�@���邱�ƂŁA�Y��P�����ȓ��ɂ͖��̕��ɍĂѕГ��ɂ�����܂��B �@�@���A�D�P/�������ł͈��S�����l�����ē�����ł���g���v�^�����܂� �@�@�g�킸�ʂ̂���ŗ������Ƃ������̂ł����A��ΓI�֎~�ł͂���܂���B |
|||||||||||||||||||||||||
| A. �Г��ɂ̑����͌��ǂ��g�������Ԃ̎��Ɍ���₷���Ȃ�܂��B �@�@�Ⴆ�A�ْ�����J�����ꂽ���ɂ͌����_�o�̍�p����܂�̂� �@�@���ǂ��g�����₷���Ȃ�A�A�ƌ��T���ɑ����̂͂��̂��߂ł��B �@�@���̑��A���NJg���̗U���v���Ƃ��ẮA�A���R�[���A�`���R���[�g�Ȃǂ̐ێ�A �@�@��_�f��ԁi�l���݁A�G���A������c����b�V�����̒ʋΓd�ԂȂǁj�A �@�@�ُ픭���i���M�A���V���A�}���ȉ��x���Ȃǁj�A�x���̐Q������i�ጌ���j �@�@�Ȃǂ�����܂��B����\�h�ɂ͂������Ȃ�ׂ��������H�v���K�v�ł����A �@�@���ǎ��k��p�̂���J�t�F�C�������̐ێ��ċG�̐������\�h���ʂ�����܂��B �@�@�܂��H���ł̗\�h�Ƃ��Č��ʂ��F�߂��Ă���̂̓}�O�l�V�E���i�C���ށj�� �@�@�r�^�~��B2�i�[���A�����A���o�[�Ȃǁj�ŁA�������Ȃ��悤�ɐS�����Ă��������B |
|||||||||||||||||||||||||
| A. �A�C�X�N���[���₩���X�ȂǁA�₽�������}���ŐH�ׂ�ƁA���߂��݂�O������ �@�@�L�[���ƒɂ��Ȃ邱�Ƃ�����܂��B���̓��ɂ��A�C�X�N���[�����ɂƂ����܂��B �@�@����͑��̂ł͂Ȃ��Aice cream headache�Ƃ��������Ȉ�w�p��ł��B �@�@���̔����@���͍��̂Ƃ���2�̐�������܂��B��͋�����h������� �@�@���̌��ǂ��}�Ɋg�����Ĉꎞ�I�Ɍy�����ǂ�������Ƃ������ǗR���� �A �@�@������͗�h������������Ɨ₽����`����_�o�����łȂ��A�ɂ݂�`���� �@�@�_�o������Ďh������Ă��܂��Ƃ����_�o������������܂����A�͂�����Ƃ��� �@�@�a�Ԃ͂܂��킩���Ă��܂���B�ǂ���̐��ɂ��Ă��T���ȏ�͑������Ƃ��Ȃ��A �@�@���炾�ɂ������e���͎c��Ȃ��ƍl�����Ă��܂��̂ŐS�z�͂���܂���B �@�@���̑��ɂ��H�i�֘A�̓��ɂƂ��āA�A���R�[���U�����Ɂi�����^�ƒx���^�j�A �@�@�O���^�~���_�i�g���E���U������(���ؗ����X�nj�Q�j�Ȃǂ�����܂��B |
|||||||||||||||||||||||||
| A. �n�����d�ǂɂȂ��῝�◧������݂��܂����A�����̏Ǐ�� �@�@���Ɍ����u�]�n���v�ƌĂ����̂ŁA��ʓI�ɂ� �����_�o��Q�� �@�@��Â����̂��قƂ�ǂł��B����̎��ɓ|�ꂽ��A�N������}�� �@�@�����オ�������ɋN����N�����ጌ���Ȃǂ͂��̓T�^��ł���A �@�@�X�g���X���J�̒~�ρA�����s���A�����O�ł��悭�݂��܂��B �@�@�u�]�n���v�͈ꎞ�I�Ȍ����ቺ�Ŕ]�����錌�t�ʂ��s�����錻�ۂł���A �@�@����ɑ��Ĉ�w�I�ȁu�n���v�͐�Ηʂ��s�����Ă��邱�Ƃ��w���܂��B �@�@���ɐԌ����Ɋ܂܂�錌�F�f�i�w���O���r���j�ʂ��d�v�ŁA����� �@�@�_�f��̂̋��X�܂ʼn^�Ԗ�ڂ�S���Ă��܂��B�]���Ă��̉^�щ��� �@�@����Ƃ����_����ԂɊׂ邽�߁A����A���@�A��ꂪ���Ȃ��A �@�@�S�g�����邢�A�̂��₦��A���ɁA��F�������Ȃǂ̏Ǐo�Ă��܂��B �@�@���ꂪ�u�n���v�̏Ǐ�ł��B�܂������́u�₦�ǁv�̏Ǐ�ł�����A �@�@�����̋��ʓ_������܂��B ������ɂ��Ă����̗l�ȕn�����ۂ��Ǐ�� �@�@�n���ȊO�̕a�C�ł��悭�݂���̂Ŏ��Ȕ��f�������̈�Ë@�ւ� �@�@��f���Ă݂Ă��������B |
|||||||||||||||||||||||||
| A. �n���̑啔���͓S�s���������ł��B�Ԍ����̎����͖�120���ł��̂ŁA �@�@�������肵���S���̐ێ悪�K�v�ƂȂ�܂��B���q�˂̓��e�ł� �@�@�ޗ��i�S�܁j���ߏ苟������Ə��i�i�w���O���r���j�͐��Y������ł����� �@�@�H��i�����j�͂�����Ƌ@�\���Ă���͂��ł��B�Ȃ̂ɂ�������Ȃ��Ȃ�̂� �@�@�@����̃X�s�[�h����������i�o���j���A�����I�ȍޗ��s������Ȍ����ł��B �@�@�@�̌����͈ݒ�����o��������́i�ݏ\��w����ᇁA�咰�|���[�v�A�݊��A �@�@�咰���A���Ȃǁj�Ǝq�{����o��������́i�ߑ����o�A�q�{�؎�Ȃǁj�� �@�@���̑�\�ł��B�܂������ł͔D�P�A�o�Y�A�������ɂ��S���������܂��B �@�@�A�̌����͖����I�ȓS���̐ێ�s����z����Q�ł��B�܂�ߌ��� �@�@�_�C�G�b�g������H�����A�����s�����S�s���������Ă���Ǝv���A �@�@�ŋ߁A�Ⴂ�����̕��𒆐S�ɋ}�����Ă��܂��B �@�@�ӎ����ēS����ێ悵�Ă���̂ɕn�����J��Ԃ��ꍇ�́A�w�l�Ȍ��f�� �@�@�ݒ��̓������������Ă��������K�v������ꍇ������A�̑���t���� �@�@�����Ă��n�����i�s���邱�Ƃ�����̂ŁA����Ë@�ւ���f���Ă��������B �@�@���@�ł͕n���̃g�[�^���T�|�[�g�ɏ�M�𒍂��ł���܂��̂ł����k���������B |
|||||||||||||||||||||||||
| A. �ȑO�͂�����R�[�q�[�Ɋ܂܂��^���j�����S�ƌ������� �@�@�z����j�Q����̂ł悭�Ȃ��ƌ����Ă��܂������A�ŋ߂ł� �@�@�����ɐێ悵�Ă����ʂɈႢ�͂Ȃ����Ƃ��������Ă��܂����B �@�@���̗��R�Ƃ��āA�ŋ߂̓S�܂͏����܁i�������n���o����j���嗬�ŁA �@�@�S�̊ܗL�ʂ��������߃^���j���̉e����w�ǎȂ��Ȃ�܂����B �@�@�����S���R���n���̕��́A�S���̋z���\�����܂��Ă��邽�߁A �@�@������R�[�q�[�ƍ��킹�Ă��A���̌��ʂ͕ς��܂���B �@�@�܂�����̎��ԑт�1��1��ł���Β��ł���ł��H�O�ł��H��ł� �@�@�卷�͂���܂���B���܁A�݂ɍ���Ȃ�������������Ⴂ�܂����A �@�@���̏ꍇ�͏A�Q�O�ɕ�����A�ݖ�p���Ă����܂��܂���B |
|||||||||||||||||||||||||
| A.
�n�������P����ɂ͓S������������ۂ�����Ƃ����킯�ł͂���܂���B �@�@�܂��A���������P���ɕK�v�ȓS���́A���o�̂��鐬�l������12mg�A �@�@�D�P��������20mg�A�o���10mg�A�j����10mg�Ƃ���Ă��܂��B �@�@���̂Ȃ�S�͔�r�I�z������ɂ����h�{�f�ł���A�̓��ɗ��p�����̂� �@�@�ێ�ʂ̖�10���ɉ߂��Ȃ�����ł��B�S���ɂ̓w���S�i���ށA���ށj�� �@�@��w���S�i��ؗށA���ށA���ށA�C���ށA�L�ށA���j������A�O�҂̕��� �@�@�z�����͗D��Ă��܂��B��������҂ł��ǎ��̃^���p�N���A�J���V�E�� �@�@�r�^�~��C��B�Ȃǂ��ꏏ�ɐێ悷�邱�Ƃŋz�������A�b�v���܂��B �@�@�]���ĐH���̊�{�͂����܂ł��K�v�ȉh�{�f���o�����X�悭�ۂ邱�ƂȂ̂ł��B �@�@���݂ɓS�𑽂��܂ސH�i�����ɂ��������܂����̂ł��Q�l�ɂ��Ă݂Ă��������B |
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| A. �Ⴂ�����̕��ł͎l���̖��[�̗₦�����|�I�ɑ����݂��܂��B �@�@����20�`30��ł͎��⑫��̗₦�����S�ł����A �@�@40�ΑO��ɂȂ�ƁA�t�Ɏ�̂Ђ�⑫�̗����قĂ��Ă������ �@�@�����Ă��܂��B�������Ȃ�킯�ł�����₦�͎������Ǝv�������ł����A �@�@���͂��̏ꍇ�ɂ͂�����G���₦�n�߂Ă��邱�Ƃ������̂ł��B �@�@�����čX�N���߂��ɂȂ�Ɓu�₦�̂ڂ��v�Ƃ�����Ԃ������݂��܂��B �@�@����͉����g�A���ɑ���悪�₽���Ȃ�A�t�ɏ㔼�g�� �@�@�̂ڂ����Ԃ������܂��B�X�ɍX�N���ȍ~�ɂȂ�Ɨ₦�������镔�ʂ� �@�@�̂̒��S���Ɉڂ��Ă��邱�Ƃ������Ȃ�܂��B�[���̉��̒ቺ�ɂ�� �@�@�����̗⊴���N�����Ǐ���������悤�ɂȂ��Ă��܂��B �@�@���̗l�ɔN��Ƌ��ɏ����z���������ω����邽�߁A�Ǐ���������� �@�@�ς���Ă������Ƃ������̂ł����A������̐���ł����ʂ��Ă���_�́A �@�@���m��w�́u���Łv�Ƃ����a�ԂɊ�Â����̂��啔�����Ƃ������Ƃł��B �@�@���{�l�̗₦�ǂ́A�������������݂ɂ����̂��������߁A �@�@���������܂����P���Ă����Ȃ��ƁA�������߂������ł͉������Ȃ��̂ł��B |
|||||||||||||||||||||||||
| A. �u�����₦�ďn���ł��Ȃ��v�u�R�^�c����o���Ȃ��v �@�@�u�g�їp�J�C����������Ȃ��v�ȂǁA �₦�̏Ǐ�� �@�@�~�ɏo������Ǝv��ꂪ���ł����A�ŋ߂ł͐^�Ă� �@�@��������P�[�X�������Ă��܂����B��[�̂悭������ �@�@�E��� �����ԃf�X�N���[�N���������鏗���̒��ɂ� �@�@�₦�݂̂Ȃ炸�ɂ݂�i�������������������܂���B �@�@�Ƃ��낪�A���̂悤�Ȑh���Ǐ������ĕa�@����f���Ă� �@�@�����ɐf�Ă��炦�邱�Ƃ͏��Ȃ��A�y�����ꂪ���ł��B �@�@���̂Ȃ琼�m��w�ɂ́u�₦�ǁv�Ƃ����T�O�����݂��� �@�@����Ƃ��������Ö@���Ȃ�����ł��B�t�ɓ��m��w�ł� �@�@�ƂĂ��d�v�ȕa�ԂƂ��đ����A���P�ɗL���Ȋ����� �@�@�������p�ӂ���Ă��܂��B�܂� �u�₦�ǁv�̎��Â� �@�@�����ł����ӂȕ���̈�ł���A ������̎��� �@�@�������̂𑱂���A8���ȏ�̐l�ɉ��P�������܂��B�@�@�@�@ |
|||||||||||||||||||||||||
| A. �h�{�o�����X�̂Ƃꂽ�H�����A������x�K���I�ɐۂ� �@�@���Ƃ͌����܂ł�����܂��A���Ɂu���̈���v�� �@�@��ɂ��܂��傤�B���͑̉����ӂ��Ⴍ�̂��܂� �@�@�����Ă����ԂȂ̂ŁA�����□�X�`�A�X�[�v�Ȃ� �@�@���������̂����ɂ��邱�Ƃő̂�ڊo�߂����Ă��������B �@�@�H�ނɂ��ẮA�g�n�ō̂��썑�̉ʎ����� �@�@�̂��₵�A����n�ō̂����̂͑̂����߂܂��B �@�@���̕\���Q�l�ɂ��Ă݂Ă��������B �@�@�@ |
|||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| A. �u���܂ł��������Ď�X�����S��̂ł��肽���v�B����͐��̏������F�A�肤���Ƃł��B �@�@�Ƃ��낪��ʓI�ɂ͂R�T���߂��鍠���炨���̐������}���Ɋ����n�߂Ă��܂��B �@�@����͔������Ȃ����Ƃł����A�H�v�������ł͘V���͋����قǒx�点�邱�Ƃ� �@�@�ł��܂��B �@�@�A���`�G�C�W���O�������I�ɑ������ꍇ�ɏd�v�Ȃ̂��u�����v�Ƃ����T�O�ł��B �@�@�����u�̂ƐS�̓��ʂ����N�ł���A���┧��������ۂ��N�������X����������v �@�@�Ƃ����l�����ł��B�X�g���X��������傫���⎞�Ԃ��V���̃X�s�[�h�� �@�@�������Ă���̂ł��B �@�@�X�g���X���y�������邽�߂ɂ͗]�ɂ̉߂��������d�v�ł��B�u�Z���Ղ���v�� �@�@�ǂ�ȂɖZ�����Ă��A�܂��͂��������y�����߂������̎��Ԃ���邱�Ƃł��B �@�@���ɂ̓A���}�Z���s�[�ȂǂŃ����N�[�[�V���������I�Ɏ�����ĕs���̔g�� �@�@���߂ɉ�����邱�Ƃ����ʓI�ŁA������悢�A���`�G�C�W���O��ƍl���Ă��܂��B �@�@�܂�����������������ړI�ɂ�������P�A���邱�Ƃ� �@�@�ӂ�Ȃ��悤�ɂ��Ă��������B |
|||||||||||||||||||||||||
| A. ����̐H���ɂ���ĐS�g�̐�����₢���N���ێ�����u�H�{���v�͂ƂĂ��d�v�ł��B �@�@�V�O�ɂ��ĂP�V�̔���ۂ��Ă����Ƃ����������������̐����@�̕s�V�����̈�b�� �@�@���܂�ɗL���Ȃ��b�ł����A��������w�Ԃ��ƂƂ��āA�@�C�̂��́i�L�A�C�V�j�A �@�@�A�������́i�����A���S�}�A�������炰�A�C�ہj�A�B�S��̂�����́i�R���A�I�N���j�� �@�@���������H�ׂ邱�Ƃł��傤�B �@�@��������g�߂ȐH�ނł��̂ŐϋɓI�Ɏ�����Ă݂Ă��������B �@�@�܂��H�ވȊO�ŋ{���̏�����������X������������ۂ��߂ɍs���Ă������ƂƂ��āA �@�@�������������ċz�@�ŋC������Â߂��肷�邱�Ƃ��m���Ă��܂��B �@�@�����́A���ꂼ��A���}�Z���s�[��K�Ƃ��Č���Ɏp����Ă���Ǝv���܂��B |
|||||||||||||||||||||||||
| A. �A���}�Z���s�[�͌Â����牢�B�𒆐S�ɔ��W���Ă������Ö@�ŁA �@�@�g�F���Ö@�h�Ƃ������܂��B �@�@�g�F���h�Ƃ����ڂɌ����Ȃ����R�̎����͂��g���ĐS�g�̌��N����e�� �@�@���i����{�p�ł��B �@�@�����w�ɂ����Ă��A�A���}�Z���s�[�͏����̊F�l��������l�X�ȕs���ɑ��āA �@�@�ƂĂ��D�ꂽ���Ö@�Ȃ̂ł����A�c�O�Ȃ�����{�̈�ËƊE�ł̔F�m�x�͒Ⴍ�A �@�@�u��ֈ�Áv�Ƃ������Ɏア�ʒu�Â��ɉ�������Ă���̂�����ł��B �@�@����I�ȃA���}�Z���s�[���������������ƂŐS�g�Ƃ��Ƀ��t���b�V������܂����A �@�@������p���Ă��������ƍX�ɂ��̑�����ʂŔ��Q�̌��ʂ�������͂��ł��B |
|||||||||||||||||||||||||
| A. ��ÂƔ��e�̗Z���ŁA�����̊F�l�̔��ƌ��N���g�[�^���T�|�[�g���Ă����T�����ł��B �@�@�S���I�ɂ��ނ����Ȃ��S���V�����X�^�C���̈�Ìn�G�X�e�T�����ŁA �@�@���@���S�ʃv���f���[�X�������܂����B���f�B�J���i��ÓI�j�A���}�g���[�g�����g�ł́A �@�@�����̊F�l��������l�X�ȕs���ɑΉ��ł���I�C�����j���[����葵���Ă���܂����A �@�@���Ɂu�����֔�v��u�₦�ǁE�ނ��݁v�ɂ͓��ʃ��j���[���������܂��B �@�@���̑��ɂ��A���`�G�C�W���O�P�A���C���̃��j���[���L�x�ł����A �@�@�P�Ƀ����N�[�[�V�����Ƃ��Ẵ��C�������p�ӂ������Ă���܂��B �@�@�Z���s�X�g�͑S���o���L�x�ȏ����X�^�b�t�ł����A����� �@�@���@���S�ʓI�Ƀo�b�N�A�b�v�������܂��̂ň��S���Ă����������܂��B �@�@�ǂ��������p���������B�ڂ����́u���[�u���[�Y�v�̃z�[���y�[�W���������������B |
 |
|
| A. �����̏ꍇ�͖�肠��܂���B�ނ��땹�p�ɂ���� �@�@ �@�@��Ǐ��łȂ������Ǐ�������ɉ������邱�Ƃ�����A �@�@�����ǂ̗\�h�ɂ����ʂ��F�߂���ꍇ������܂��B �@�@�X�ɁA�R�������Ɗ�����͑������悢���Ƃ������A�܂� �@�@�X�e���C�h�܂ƎČӍ܂͍ł����ʓI�ȕ��p��ƌ����܂��B �@�@�������A���ɂ͂ƂĂ������������g�ݍ��킹������܂��B �@�@�Ǐ���������A�d��ȕ���p����������댯������A �@�@��p����ꍇ�͎�f���ɗ\�߂��m�点���������B |
|
| A. ������͂��炭���ݑ����Ȃ��ƌ��ʂ����҂ł��Ȃ��� �@�@�v��ꂪ���ł����Ƃ�ł�����܂���B���e�ɂ���Ă� �@�@�P�O�������Ȃ������Ɍ��I�ɉ��P������̂��炠��܂��B �@�@�����Ƃ�����͋}���̏Ǐ�̏ꍇ�ł����āA�����Ԃ� �@�@�����I�Ɋ����Ă����Ǐ��̎����P��ړI�Ƃ����ꍇ�� �@�@���ʔ����̂��߂ɂ�2�`4�T�Ԃ̌p�����p���K�v�ł��B �@�@�����ڂ�����n�߂܂��ƁA���̏�Ԃ����肳������Ԃ� �@�@�X�ɕK�v�ƂȂ�܂��̂ŁA�ł炸���C�悭���ݑ����܂��傤�B |
|
| A. ���@�ł͂��ׂĕ��₷���G�L�X�܂ŏ������Ă���܂��B �@�@���̂܂ܒʏ�̕���̂悤�ɐ��ň�C�Ɉ���ł��悢�̂ł����A �@�@�G�L�X�܂̓C���X�^���g�R�[�q�[�̂悤�Ȓ��o���ł��̂� �A �@�@�ł���u�����v�A�܂蓒�ɗn���������̂�K�x�ɗ�܂��Ă��� �@�@���ނ̂��ł����ʓI�ł��B�����ɗn�����ƂŗL���������n���o���� �@�@�{���̐�����ɋ߂���ԂƂȂ�A�z�����������ʂ����܂�܂��B �@�@����́u�`�`���v�Ɩ������ꂽ���̂̑S�Ăɓ��Ă͂܂�܂����A �@�@���Ɂu�₦�ǁv�̎��Ì��ʂɂ͍����o�܂��̂Ő��������������B �@�@�A����O������܂��B�q�C�̋�������A�̒ɂ݂ɑ��鎡�Âł� �@�@�ނ��듒�ɗn��������ɗ�₵�ĕ��p����u�╞�v�̕������ʓI�ł��B �@�@�܂��A�u�`�`�ہv��u�`�`�U�v�͗n����������i�ܗ�U�͗�O�j���A �@�@�u�`�`���v�͓��ɗn���ď��ʂ����Ԃ��|���ĕ��������悢�ł��B �@�@�܂�����ǂ��͍ő�̌��ʂ������o���Ȃ���ł����A�H��ł� �@�@���قǖ��͂Ȃ��A�݂ɋ����l�͎��͂ނ���H��ɕ��p���Ă��������B �@�@�������ɂ����p����ꍇ�ɂ́A�����͗ǂ��Ȃ����̂�����܂��̂� �@�@���̏ꍇ�͕K����t���t���畞��w�����Ă��������B |
 |
|
| A. �ԕ��ǂ͏t�����Ƃ͌���܂���B�ԕ��̎�ނɂ���Ă� �@�@���Ăɔ���������A�H���ɕ@���₭����݂����������肵�܂��B �@�@�ʔN���A�����M�[���@���̏ꍇ�͉ԕ��LjȊO�� �@�@�n�E�X�_�X�g�A�_�j�A�J�r�A�y�b�g�̖тȂǑ��̍R���ɂ�� �@�@�A�����M�[�����Ă���l�������悤�ł��B �@�@�Ǐ�̈��������O�Ȃ̂������Ȃ̂��A���A���y�݂̗L���A �@�@�s�[�N�̎����ȂǂŐ��@�͉\�ł����A�����������̂��Ƃ����� �@�@��x�͌��t�����ł������̏��̊m�F�������߂��܂��B |
|
| A. ��l�ɂȂ��Ă�������������ɂȂ��Ԃ��ς��Ȃ��ꍇ�A �@�@����̓A�����M�[�ł͂���܂���B���̏ꍇ�� ������ �@�@�܂܂������̏����ɕK�v�ȕ����y�f���������Ă��邱�Ƃ� �@�@�����Ǐ������Ă���u�����s�ϐ��v�Ƃ����܂��B �@�@�A�����M�[�Ǐ�͖Ɖu�V�X�e�����֗^���Ĕ���������̂ŁA �@�@���o�����y�݁A�畆���y�݁A�@���]�A�@���A�Ђǂ����͚b���� �@�@�A�i�t�B���L�V�[�V���b�N�Ƃ����ċz����Ɋׂ邱�Ƃ�����܂��B �@�@�����͗��ƕ���ŐH���A�����M�[�̑�\�I�ȐH�i�ł���A���ɂ� �@�@�����A�哤�A�i�b�c�ށA���A�L�A�C�V�A�I�Ȃǂ��������܂��B �@�@�A�����M�[�̌����H�i�͌��t�����łقړ���ł��܂��B �@�@�����A�����M�[�͊ܗL�^���p�N�́u�J�[�C���v�ɑ�����̂��w�ǂł��B �@�@���c�����ɔ��ǂ��āA���̑����͊w�������ɑϐ��������܂����A �@�@�y�Ǘ���܂߂�Ɛ��l�ɂ܂Ŏ����z���ꍇ������܂��B �@�@�����A�����M�[�̕��ɒ��ӂ��Ă������������̂́A�}�������Ȃǂ� �@�@�����܂p���鎞�ł��B�����̓��_�ې��܂ł̓J�[�C�����ܗL����Ă��� �@�@����͊댯�ł��̂ŁA���̏ꍇ�͐���Ë@�ւ���f���Ă��������B |
 |
|
| A. �\�h���ʂ͐ڎ���Q�T�Ԃŏo�����A���N���߂���ƂȂ��Ȃ�܂��B �@�@�C���t���G���U�E�C���X�͖��N�A�ψق��Ȃ��痬�s���J��Ԃ��܂����A �@�@����ɑΉ����邽�߃��N�`���Ɏg�p���銔�����N�ς���Ă��܂��B �@�@�]���āA���N�ڎ킵�Ȃ��Ɨ\�h�������Ă��邱�ƂɂȂ�܂���B �@�@���s���͒ʏ�P�Q������R�����ł��̂ŁA�ڎ펞���͂P�O������ �@�@�x���Ă��N���ɂ͎Ă��������B�����G�ߌ���A���ʌ���i�� �@�@�����ҏ����ł��̂ŁA�������\���Ă���ƕi��ɂȂ��Ă��܂��܂��B �@�@�ȂǓ~����t��ɑ厖�ȃC�x���g���T���Ă�����͂����߂� �@�@���\�������B���@�ł̗\���t�J�n���◿���ɂ��Ă� �@�@���N�A��قȂ�܂��̂ŁA�ڂ����͐V�����ł��m�F���������B |
|
| A. �ڎ�ł��܂��B�C���t���G���U���N�`���̓E�C���X�̕a�������Ȃ����� �@�@�s�������N�`���ł���A�َ��ɉe����^����Ƃ͍l�����Ă��Ȃ����߁A �@�@�D�w����͐ڎ�s�K���҂ɂ͊܂܂�Ă��܂���B �@�@�A���A�D�P����(�P�Q�T�܂Łj�͎��R���Y���N����₷�������ł���A �@�@���̎����̐ڎ�͔����������悢�ƍl�����Ă��܂��B |
|
| A. �����w����̓C���t���G���U���N�`����ڎ킵�Ă��x��͂���܂���B �@�@�s�������N�`���̂��߃E�C���X���̓��ő����邱�Ƃ��Ȃ��A �@�@�������Ă��q����ɉe����^���邱�Ƃ�����܂���B �@�@�܂��A�������Ԓ��ɃC���t���G���U�E�C���X�Ɋ������Ă��A �@�@�������ē����ɂ͊����͂��Ȃ��ƍl�����Ă��܂��B |
|
| A. C�^�̉����N�`���͌��݂܂��J������Ă���܂��A �@�@B�^�̉��������o�H�����t�ł��̂ŁA�ڐG�̊댯�x�������Ȃ���� �@�@���Ə��̎w�肪�Ȃ�����͓��ɕK�{�ł͂���܂���B �@�@���s���̉��̑啔����A�^�ł��BA�^�̉��͌o�������ł��̂� �@�@��������\�h�ڎ�����Ĕ�����K�v������܂��B �@�@���������x�̊��ԂȂ� ����ƂS�T��̂Q��ŏ[���ł����A �@�@�Q�C�R�N�ƂȂ�Ɣ��N��̂R��ڎ킪�K�v�ł��B |
 |
|
| A. ���@�œ������������Z�b�g���ꂽ�R�[�X�́u�V��v�u�����v�u�����v�� �@�@�R�ł��B�݂ł��咰�ł����e�ɂ���Ă͐��m�Ȑf�f�̂��߂� �@�@�g�D�̃T���v�����O�����{����K�v������������ꍇ������܂��B �@�@���ɑ咰�ł͌������ɂ��̏�Ő؏����ׂ��|���[�v�������� �@�@�P�[�X������������܂���B�h�b�N�̓����������ł��̂悤�� �@�@�lj����u�����������ꍇ�A���������Ȃ炻�̒lj����݂̂��A �@�@�|���[�v�؏��Ȃ猟�������Âɕς�邽�߂Ɍ����s�ׂ��̂��̂� �@�@���̎��_�Ŏ��R�f�Â���ی��f�Âɐ�ւ��܂��B �@�@�ł�����S�̂̔�p�͂���قǑ傫���͕ς��Ȃ��Ƃ��l���������B |
|
| A. �������\�ł��B���@�͈�ʐf�Â̒��Ɍ��f�g��݂��čs���� �@�@���܂��̂ŁA�ނ���1,2�����ɕ�����Ă��ɂȂ��Ă��������̂� �@�@��낵�����Ǝv���܂��B���@�̓����Ƃ��܂��Ă͌������e���j���� �@�@�����قȂ�_�ł��B�܂����������l�ł��j���Ԃ�N��ɂ���āA �@�@����l�� �قȂ�_����������������Ĕ��肢�����Ă���܂��B �@�@�X�ɑ��]���ɂ͂���l���Ɉ�������t��p���āA�l�Ԗ����� �@�@�\���ŃR�����g�����Ă��������Ă���܂��B�܂��߂������ɂ� �@�@���f�X�y�[�X�̊g�����v�悵�Ă���܂��̂ł����p�������B |
Copyright (C) 2008 �����ݒ��ȓ��Ȉ�@. All Rights Reserved. �b���₢���킹�b�T�C�g�}�b�v�b

